![]()
![]()
【筆跡鑑定の誤りは何故発生するのか(その2)】 |
■筆跡鑑定の3つのプロセス 前回は、筆跡鑑定のスタートであるところの、「文字が紙に記されるまでの流れ」に ついて、純粋に行動分析的な角度から掘り下げました。今回はその続編です。 前回、筆跡鑑定を成り立たせている最も重要にファクターは、「筆跡の恒常性」であ ることを述べました。恒常性とは、何回書いてもほぼ同じ字形があらわれることを言い ます。これがなければ筆跡鑑定は成り立ません。 多くの鑑定人は、恒常性があるのは知っていますが、「何故、恒常性があるのか」と いうその根拠を明確には認識していない様子です。そこから、初歩的な誤りも生まれて います。 続いて、私たちがある文字を書こうとしたとき、私たちの脳は、それをどのように受 け持っているのかを説明しました。この原理が分からないと、書き手に固有の「筆跡個 性」も、鑑定を難しくしている「個人内変動」も理解しにくいからです。今回は、続き を述べます。 筆跡鑑定はつぎの3つのプロセスに分けられます。 ①筆跡個性の特定 ②特定したその筆跡個性を対照筆跡と比較すること ③異同の判断 この3ステップの中では、最初の「筆跡個性の特定」が最も難しく、また重要です。 この特定がしっかりしていないと、比較も異同判断も意味をなさないからです。いわば、 筆跡鑑定の要ともいえます。それだけに鑑定書で揉めるのはこれが多いのです。 揉めるのは、筆跡個性でもなんでもない「単なる字形の違い」を、別人の筆跡個性だ と主張する鑑定人がいるからです。「筆跡個性」と「字形の違い(個人内変動)」を混同 してしまうわけです。個人内変動とは、同じ人が同じ文字を書いたときに生じる字形の 違いです。 人間はゴム印ではありませんから、書くつどに字形が微妙に変化します。これが筆跡 鑑定を難しくしている最大の要因です。何が難しいのかといいますと、個人内変動は人 により違いが大きいからです。 それこそ、ゴム印の如く安定した人のいる一方で、書く都度に別人の筆跡かと思うほ ど変化をする人もおります。加えて高齢化社会でもあり、老齢による筆跡の乱れや、痴 呆症の影響なども増えつつあります。 ■どうすれば「個人内変動」を特定できるのか それでは、単なる変化である個人内変動を排除し、正しく筆跡個性を特定するために は、どのようにすればよいのでしょうか。 まず、第一には、1文字で判断するのでなく、少なくとも2~3文字を並べてみて観 察する必要があります。筆跡からある特徴を発見したとしても、1文字では、個人内変 動なのか、それとも固有の筆跡個性なのかは判断できません。 2文字、3文字に同じ特徴が発見出来て、初めて、それは、書き手固有の筆跡個性だ といえるわけです。 しかし、多くの鑑定人は、1文字で判断し、筆跡個性だと主張します。何故でしょう か。……警察OBの鑑定人が多いのですが、彼らは、意図的な人は除いても、ここで述 べているような理論を知らないためだと思われます。 私が、このようにはっきり言うのは、警察の筆跡鑑定のリーダーともいえる著名なY 氏すら、筆跡個性と個人内変動を混同していたからです。Y氏は筆跡鑑定の教科書にも なっている鑑定の実務書を著した、科学警察研究所のトップです(今はOBですが)。私 はそのY氏と実際の事件で対決した経験があります。 その事件は、怪文書を巡る事件でしたが、Y鑑定人は、その怪文書からある1字を取 り出し、8文字もある対照資料と比較して異筆としていました。つまり、1字からでは、 筆跡個性を確実には特定できないというセオリーを無視したということです・ そもそも、その容疑者は、乱れの強い筆跡であり、指摘したその特徴は乱れの結果… …つまり個人内変動です。鑑定のセオリーからは、8文字もある対照資料から共通する 特徴……即ち固有の筆跡個性を抽出する必要があるわけです。 私はそのことを主張し、実際に、その8文字から安定した筆跡個性を取り出し、それ を怪文書の筆跡と照合して同筆としました。この事件は、幸い、裁判長にも理解してい ただきました。 警察系鑑定人の頂点に立つような方すら、このような誤った鑑定をするのですから、 その下で教わった警察系鑑定人は推して知るべしであると思っています。 私の見るところ、多くの鑑定人は、筆跡が記されるその原理を理解してはいない様子 です。たとえば、「筆跡の恒常性」は知っていますが、なぜ恒常性があるのかの原理を 知らないのでしょう。 ■何故、個人内変動が出るのか 個人内変動についても、ただ漠然と考えるのではなく、個人内変動はどのようにして 発生するのか、そのメカニズムを理解することが必要です。これは、私たちの日頃の行 動を考えてみれば分かります。 私たちは毎日、無意識に様々な行動を取っています。それは、大まかには共通したパ ターンですが、緻密に観察すれば、全く同じではないということはお分かりになると思 います。このような傾向は文字も全く同じです。 たとえば、ありふれた日常行動として「シャツを着る」という行動を考えてみてくだ さい。袖を通そうとして腕を持ち上げますが、毎回、同じ高さに腕を持ち上げるという ことはありません。 あるときは、元気よく腕を90度以上に上げるときもあれば、体がだるくて低い位置 にしか上げないこともあるでしょう。別に急ぐ必要はなくとも、素早く着ることもあれ ば、ダラダラと時間をかけて着ることもあります。人の行動にはこのような変化があり ます。 文字を書くのも行動の一環ですから、同じように変化します。つまり、私たちは、元 気な時と疲れたとき等の肉体的な条件の違いがあり、あるいは気分の変化があり、行動 は、そういうものから常に影響を受けております。 文字を記すという行動も全く同じです。元気よく、あるいは気分よく書くときもあれ ば、疲れて、あるいは気分が落ち込んで書くこともあります。元気がよいときと、疲れ ているときの文字が同じということはありません。このようにして「個人内変動」が生 まれます。 ■記された文字は「運筆」の結果である 第二に難しいのは、個人内変動には、変動の出やすい箇所と出にくい箇所があるとい うことです。その違いを理解するには「運筆」(手の動かし方)というものの存在を理解 することが必要です。 形として表れる文字(字形)は、細かくいえば運筆の結果表れます。換言すれば、文字 とは、「運筆が原因で字形は結果」ということになります。 ついでなので申し上げますが、それでは運筆の元は何でしょうか。それは人の個性 (主に性格や習慣)です。それらが、意識できない脳を通じて文字を表出させるわけです。 そう考えるとある字形が顕在化するのは、人の個性が真実の原因(真因)となり、それ が運筆を生み、運筆により字形が表れるということになります。つまり、つぎのような 流れになります。 人の個性――――>運筆――――>形としての文字
(真因) (原因) (結果) このように考えると個人内変動とは、「運筆に影響を及ぼす要因により発生する変 化」と考えることができます。そこで、今度は運筆に影響を及ぼす要因とはどのような ものか……ということになります。1部述べてきましたが、運筆に影響を及ぼす主な要 因は次のようなものがあります。 ①肉体的条件……若くて柔軟であるとか、高齢になり体が堅くなっている等の他、これ には書道の訓練の有無なども含みます。 ②精神的条件……元気溌剌としているとか、気落ちしているなどの気分の問題。 ③環境的条件……落ち着ける場所か、そうでない場所かなどの環境の状態。筆記具の別 や紙の違い。あるいは、立って書くのか座って書くのか等の条件の違い。 筆跡は、このような様々な条件の影響を受けて、微妙に変化します。その変化が個人 内変動です。 ■個人内変動で変化しやすい箇所としにくい箇所 しかし、ここからが肝心なのですが、文字は、その字画構成によって、影響を受けや すい箇所と受けにくい箇所があります。これについては、「大」という文字を使って説 明いたします。 「大」字の場合、横画の長さや両払いの長さなどは容易に変化してしまいます。実際 は、「大」字に限ったことではなく、字画線や払いの長さは、変化しやすいものの代表 です。それは何故でしょうか。 それは、それらの画線を短く書こうが長く書こうが「運筆」の面からは何も変える必 要がないからです。つまり、手の同じ姿勢や動きから、長い線も短い線も書くことがで きます。 ゴルフのパットにたとえれば、距離の長さによって腕の動き……つまりストロークは 変化します。しかし、パターを握った手を変化させる必要はありません。それと同じこ とです。 横線でも、左右の払いでも、短く書こうが長く伸ばそうが、手の使い方は、何も変化 させる必要がありません。そのような状態だと、字形に影響を及ぼす3条件…「肉体的 条件」、「精神的条件」、そして「環境的条件」の影響を受けやすくなると考えられま す。図形をご覧ください。 「基本の筆跡」とは、この書き手の基本的なパターンです。それが右のように、縦に 長くなったり、横広になったり、あるいは両払いが長くなるなどは簡単に変化してしま います。つまり、容易に個人内変動が発生するということです。 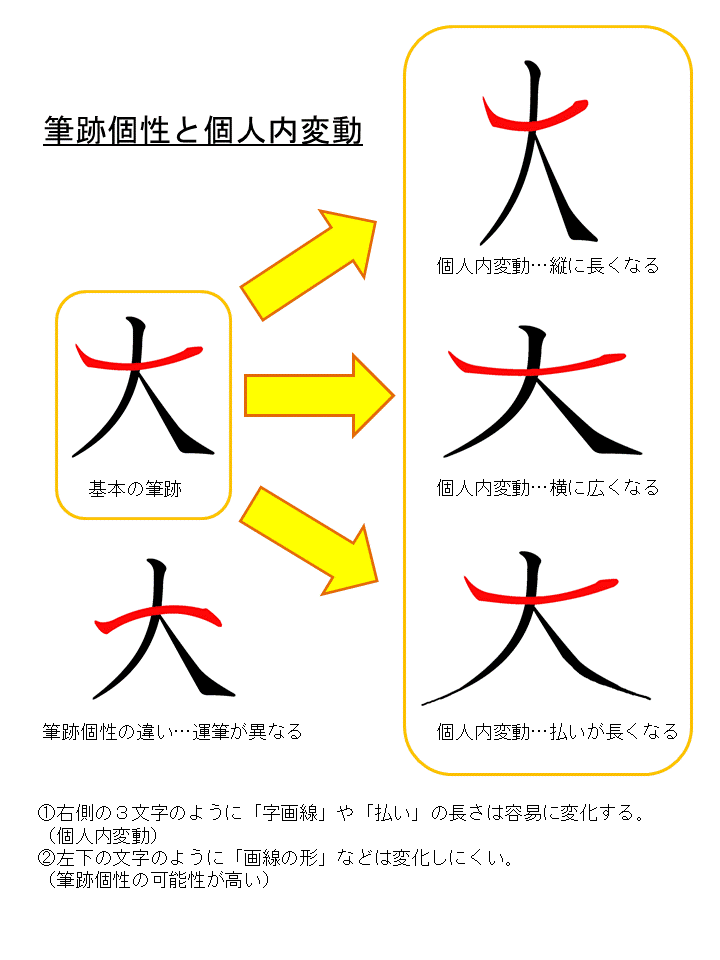 たとえば、記入するスペースが横方向に窮屈なら縦長文字に、縦方向が窮屈なら横広 の潰れたような字形に変化します。これは環境条件の影響です。また、左右の払いは、 気分が良いと長めに伸ばしたり、逆に気落ちしていたりすると短めに書いてしまいます。 これは、精神的条件の影響です。 しかし、左下の文字のように、横画が「皿」型から「ドーム」型に変化するとしたら どうでしょうか……。これは、容易には変化しません。何故でしょうか。これは、運筆 (手の使い型)が異なるからです。 つまり、皿型に書くのとドーム型に書くのでは、「手首のヒネリ方」がまるで違うこ とになります。このような状態から生じた字形の違いは、筆跡個性(性格や習慣化した 行動傾向)の反映です。つまり、このような、字形に現れた特徴こそ筆跡個性というこ とになります。 このように、筆跡個性の影響を強く受ける部分は、肉体、気分、環境の違いなどの影 響は、相対的に小さくなると考えられます。このように、文字を構成している字画線は、 その形状により、個人内変動が強く影響したり、影響を受けなかったりするなるわけで す。 さらに、図には書いていませんが、例えば左右の払い、この微妙な曲線は、高齢にな り筋肉や関節が堅くなると書きにくくなります。つまり、滑らかな曲線ではなく、ゴツ ゴツした線になったりします。震えが出るということもあります。これは肉体的条件の 影響です。 ■筆跡とは「複雑系」 筆跡というものをこのように理解してきますと、筆跡というものは、本質的には「還 元論」で解明できるようなものではなく、「複雑系科学」の分野そのものであるという ことが再認識されます。 複雑系とは、「相互に関連する複数の要因が合わさって、全体としてなんらかの性質 を見せる系であり、その全体としてのありようは、個々の部分からは解明できないも の」と定義されております。 そして、その分野には、身近なものでは、「経済現象」や「気象」、そして、ヒトの 「神経系」などがあります。 また、複雑系科学の生い立ちは、アリストテレスの「全体とは部分の総和以上の何物 かである」という思想までさかのぼるものと言われます。これは、まさに「筆跡」とい うものの本質だと思います。 筆跡とは、「個性」や「社会」「教育」等々の影響を受けつつ、「ヒトの神経系」が 生み出すものですから、まさに複雑系そのものでしょう。筆跡鑑定の本質は、名画の真 贋鑑定のような感性も必要な職務です。 従ってこの分野は、現在も相当な将来も、還元主義的アプローチでは解明はできない ものだと考えます。それはコンピューター鑑定の困難さにもつながることだと思います。 このことを考えますと、わが国の筆跡鑑定が最高裁で認められた昭和41年の判決の なかで、補足的に言われた「今後はより科学的な鑑定技術の開発が望まれる」との文言 は、そう容易なことではないことが分かります。 従って、筆跡鑑定については、今回述べたような、「筆跡が紙に記されるまでのプロ セスを理解」したうえで、その複雑さを認識し、「複雑なものを複雑なままで理解しよ うとする虚心な姿勢」が必要なのだと考えます。 筆跡とはなかなか厄介なものですが、このあたりについて、弁護士先生はじめ司法関 係者のご理解が深まることを心から期待しております。 この項終わり |
| 一般社団法人・日本筆跡鑑定人協会 株式会社・日本筆跡心理学協会 代表 筆跡鑑定人 根本 寛(ねもと ひろし) 東京都弁護士協同組合特約店 関連サイト http://www.kcon-nemoto.com 事務所 〒227-0043 神奈川県横浜市青葉区藤が丘2-2-1-702 メール kindai@kcon-nemoto.com TEL:045-972-1480 FAX:045-972-1480 MOBILE:090-1406-4899 |